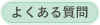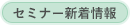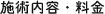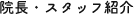Blog 2ページ目
足がつる
運動中や睡眠中などに足をつった経験をされた方も多いと思います。人によりつりやすい場所は様々ですが、ふくらはぎ・足のすね・足の裏や足の指などが多いです。
昔はふくらはぎのことをこむらと呼んでいたことからこむら返りとも呼ばれます。普段伸び縮みをスムーズに行っている筋肉が誤作動を起こし、筋肉が急に収縮をして痙攣している状態になります。
🔹原因🔹
①運動
筋肉や神経の働きを調節するにはカルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラルが関与します。汗をかくことにより汗とともにミネラルが排出され、筋肉疲労が起こりやすくなります。
②冷えや筋力不足
足の筋肉量が少なかったり、冷えて血行不良になると栄養素がうまく行き渡らないので体が熱を産生させるために筋肉が収縮します。冷えてない方に比べてたくさん収縮する必要があるので筋肉疲労が起こりやすくなります。
熱中症・脱水・脳梗塞・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・糖尿病・高血圧(薬の副作用によって)などの病気により足がつりやすくなる方もいます。
ふくらはぎの筋肉がつった場合はゆっくり足首を回したり、足先を体に向けるように背屈させたりします。硬い筋肉を伸ばすのかポイントです。痛みがとれてきたら患部をホットタオルなどで温めたり、湯船に浸かってください。
また体が脱水症状でも起こりやすくなるので水分・ミネラル補給も大切です!
ビタミンB群不足
疲れがとれない、朝すっきり起きれない、1日中だるい、口内炎やニキビが出来やすい、甘い物が無性に食べたくなる、お酒をよく飲む
このような症状が当てはまる人はビタミンB群が不足しているかもしれません😥
私達の体は食べたものが分解され栄養素となりエネルギーに変換されます。日々食べたものによって体が作られますが、エネルギーがうまく生産できないと代謝が悪くなり、疲れを感じやすくなります💦
国民健康・栄養調査によるとビタミンB群が不足しがちな方が多く、不足している方ほど体の疲れを感じています。ビタミンB群は3大栄養素である炭水化物・脂質・たんぱく質をエネルギーに代える働きがあります✨
ビタミンB群にはビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンと8種類あります。
パンやパスタ、スナック菓子やせんべい、スイーツやチョコレート、ジュースなどの糖質過多な食生活をしているとビタミンB群が糖質のエネルギー代謝に優先的に消費されます。
脳内ホルモンであるセロトニンの合成には必ずビタミンB群が必要がなので、不足すると集中力の低下や気分が落ち込みやすくなります。またお酒を飲むとアルコールを分解するためにナイアシン・ビタミンB12・葉酸が必要になるのでよく飲まれる方は慢性的に不足した状態になっています。お酒を飲むときはビタミンB群が豊富に含まれるおつまみを摂るのがおすすめです😊
ビタミンB群には肉や魚など動物性たんぱく質に幅広く含まれています。他には乳製品や卵・玄米やバナナ・さつまいもやほうれん草にも含まれています。
舌診
東洋医学では舌の色や形や舌の苔(こけ)などで体の状態を判断する舌診(ぜっしん)👅というものがあります。
🔷舌色🔷
苔を除く舌そのものの色は赤ちゃんの舌のような淡いピンク色が正常とされています。
🔹淡いピンクよりも白い
血色感がないので貧血になりやすい
🔹淡いピンクよりも赤い
体の中に熱がこもっているので、発熱時や飲酒後や脱水時になりやすい
🔹淡いピンクよりも紫
血液の流れが悪く、滞っている
🔷舌の形🔷
🔹ぼてっとして厚い
エネルギー不足なので、冷えや疲れがある
🔹小さくて薄い
栄養不足なので、虚弱体質や高齢者に出やすい
🔹舌の縁がギザギザしてる
歯痕があるので、水分代謝が悪くむくみやすい
🔹ひび割れやひだがある
水分不足や口呼吸などによる乾燥
🔹しみや黒い斑
血液の流れが悪い
🔷舌の苔🔷
白く薄い苔が全体的にあるのが正常
🔹厚い
暴飲暴食や胃の機能低下
🔹苔が黄色
甘い物や脂っこい食事が多いので、胸焼け・胃痛・便秘がある
歯を磨くタイミングで舌をべーっと出して観察してみてください😊毎日同じだと思っていた舌も体調や前日の食事内容でも変わってきます。自分の体の状態を把握するためにも健康のバロメーターとして使ってみてください。
ぎっくり腰
重たい物を持ったとき、洗顔時に前かがみになったとき、咳やくしゃみをしたときなど日常のふとした動作で突然発症して腰に激しい痛みを引き起こす“ぎっくり腰”の経験をしたことがある方も多いと思います💦
神経痛や麻痺がなくレントゲンやMRIでも異常所見がなく1ヶ月ほどで完治するものを医学的には“急性腰痛”といいます。
ドイツやイタリアでは突然襲う激しい痛みは魔女の仕業だと考えられ、ぎっくり腰のことを“魔女の一撃”と呼びます😊
腰まわりは上半身と下半身のつなぎの部分でいろんな動きに対応できるように体を支えています。腹筋や背筋などの背骨を支える筋肉のバランスが弱くなると腰の負担も大きくなります。ぎっくり腰は筋力低下や筋肉の柔軟性が低下して日頃の筋肉疲労が蓄積されて許容範囲を超えると発症します。
特に寒くなりかけの10~11月頃、1年で1番寒い2月頃、少しずつ暖かくなる3月~4月に腰に違和感を感じる方が多いです。
ぎっくり腰は再発しやすいので普段から腰痛改善のストレッチをして筋肉を柔軟にするのが大切です!
腰を反らせたり、腰を曲げたりするときに使われる腹筋と背筋のバランスが重要なのでスフィンクスのポーズや赤ちゃんのポーズがおすすめです✨
🔹スフィンクスのポーズ🔹
うつ伏せの状態で肘を床につき、肩と肘の角度をを直角にします。息を吸いながら上半身を反らして5~10秒キープします。ゆっくりと息を吐きながら元の位置まで戻していきます。
🔹赤ちゃんのポーズ🔹
仰向けの状態から息を吐きながら両膝を揃えて胸まで近づけます。膝を両腕で抱え込んで体を丸くします。数回深呼吸をした後にそのまま左右に転がり腰の筋肉を伸ばします。
まぶたのぴくつき
仕事が忙しいときや寝不足のときなど疲れが溜まってるときにまぶたが勝手にぴくぴくと動いたことはありませんか?もしかしたら眼瞼ミオキニアというかもしれません💦
目の疲れ、睡眠不足、ストレス、逆まつ毛やドライアイなどが原因で目の周りにある眼輪筋が自分の意思に反して痙攣します。通常は片側性で1回のぴくつきは数秒〜数分と短時間で治まりますが、1日のうちに何度も繰り返す場合もあります。特に今の時期は環境の変化や年度末で忙しくなる方が多いので起こりやすいです。
目元をホットタオルやホットアイマスクで温めたり、目を休めたりするのがおすすめです✨
また目頭には晴明(せいめい)、眉頭には攅竹(さんちく)というツボがあります。テーブルに肘をついて親指のはらでツボを刺激すると効果的です😊
眼瞼ミオキニアは片側のまぶたで症状が出ますが眼瞼痙攣は両側のまぶたで起こります。眼瞼痙攣には痙攣という名前がついていますがぴくぴくしません。
🔹まばたきの回数が多い
🔹目を開けにくい
🔹室内でも眩しい
などの症状があります。
また、おでこや口まわりや顎下が痙攣するのは顔面痙攣です。顔面痙攣は片側性で食べたり笑ったり話したりしているときにぴくぴくします。顔面痙攣が1日中と続くようになると日常生活にも支障が出るケースもあります。重症化を防ぐために痙攣が続く場合は脳神経外科や神経内科の受診をおすすめします。
ビタミンC
ビタミンCといえば“美白”のイメージが強いかと思いますがそれ以外にも風邪予防、疲労やストレスの緩和、肌のハリやシワ対策のコラーゲン生成の促進、抗酸化作用などビタミンCには美容と健康にとって大事な栄養素になります😊
🔹野菜や果物をあまり食べない
🔹お酒を毎日飲む
🔹煙草を吸う(家族が吸っていて副流煙を吸っている)
🔹風邪をひきやすい
🔹休んでも疲れが取れない
など上記が当てはまる人はビタミンCが不足しているかもしれません💦
健康を維持するためには1日350g以上の野菜摂取が目標とされています✨ほうれん草のお浸しが小鉢1皿あたり70gなので5皿分で目標摂取量に相当します。レタスやきゅうりなどのサラダが好きな方が多いですが、ブロッコリーや人参などの緑黄色野菜にはβカロテンやビタミンCやミネラルなどが多く含まれています。ビタミンCは水溶性なので茹でるよりも短時間でスチームで料理した方が栄養素が効果的に摂取できます。ビタミンCは熱に弱いので壊れやすいですが、じゃが芋はデンプンに守られているので栄養素が流されにくいです。
また別名「ストレスホルモン」と呼ばれる副腎皮質から分泌されるホルモンの「コルチゾール」にもビタミンCは関与します。ストレスは精神的なものだけでなく気圧や気温の変化もあります。体にストレスがかかるとコルチゾールが分泌されますが、副腎皮質が疲弊していてコルチゾールの分泌量が減ると集中力の低下や疲れやすいや無気力などの症状が出ます。その他にも飢餓スイッチが入ることで溜め込みやすくなるので太りやすい体質にも繋がります😥
そんな大事な臓器である副腎皮質もビタミンCを多く消費します💦
ビタミンCが多く含まれているものはブロッコリー、パプリカ、ゴーヤ、みかん、キウイフルーツなどが代表的です。
体の内側からも美容と健康のためにケアをしていきましょう!
寒暖差アレルギー
温かい場所から寒い場所へ移動したり、カレーやラーメンなど熱くて刺激性のある食べ物を食べるとくしゃみや鼻水が止まらなかったことはないですか?
アレルギー性鼻炎や風邪、花粉症でもくしゃみや鼻水などの症状があり似ていますが、寒暖差アレルギーによるかもしれません。
体の臓器は自律神経によってコントロールされています。寒い場所へ行くと血管は収縮し、暑い場所へ行くと血管は拡張して体温を一定に保っています。1日の気温差が激しい春や秋などに寒暖差アレルギーは引き起こされやすいです。特に1日の中でも7℃以上の差が出ると体が気温に慣れようとして負荷がかかります😥寒暖差アレルギーは医学的には「血管性運動性鼻炎」と呼ばれ、鼻の血管が広がり鼻の粘膜が腫れることにより引き起こされます。
🔷症状としてはくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、倦怠感、肌のかゆみ、蕁麻疹などがあります。
花粉症や風邪と症状が似ていますが、花粉症では目のかゆみや炎症や充血などの目の症状は寒暖差アレルギーでは起こりません。
また風邪とは発熱なし、水っぽくてサラサラした鼻水という違いがあります。
🔷寒暖差アレルギーの予防
①体感温度差をなくす
こまめに体温調節をできるマフラーや手袋を使ったり、マスクをして鼻粘膜に冷たい風が直接当たらないようにするのがおすすめです!
②筋肉をつける
寒暖差アレルギーはこどもは少なく大人の女性に多いとされています。男性に比べて筋肉量の少ない女性は体内で作り出す熱量が少ないので体温調節がしづらいです。
ふくらはぎの筋肉を手軽に鍛えることができる踵落としが効果的です。
③入浴
自律神経には興奮・緊張時に働くアクセルの役割の交感神経とリラックスした時に働くブレーキの役割の副交感神経の2種類があります。ストレス過多な現代人は交感神経が優位になりますく、生涯を通してあまりレベルが変化しませんが、副交感神経は男女ともに加齢により低下しやすくなります。体の疲れをとってリラックスするためにも38~40℃のお風呂に5分ほど浸かりましょう。
冬季うつ
冬になると甘い物が無性に食べたくなったり、集中力が続かなかったり、寝ても寝たりなかったりといった症状に心当たりがありませんか?もしかしたら今の時期特有の冬季うつかもしれません😥
うつの症状には色々な種類がありますが季節性感情障害(冬季うつやウインターブルー)は寒くなる10月から2月の間になりやすく春になる3月頃にかけて自然に回復して元気になります💪
東洋医学では全ての事柄に対して陰と陽に分ける考え方があります。陰には内・下・寒い・夜・冬・で、陽には外・上・温かい・昼・夏などの特徴があります。なので寒い冬のシーズンはどうしても内向的になりやすいです。
🔷冬季うつの症状としては
①過食
炭水化物のパンやパスタや白米、甘いスイーツを食べる傾向にあります。
②過眠
日照時間が短くなることにより睡眠を促すホルモンのメラトニンの分泌が減ります。睡眠の質が下がるので寝た気がしなくてより睡眠を取ろうと時間が長くなります。
③気分の落ち込みやイライラ
日照時間が短くなることにより幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が減るので気持ちの変化が大きくなります。
一般的なうつの症状は食欲不振や不眠になりやすいですが、冬季うつは反対に過食や過眠になりやすい傾向にあります。
🔷対策としては
①なるべく日光に当たる(光療法)
冬季うつの治療として高照度光照射法という特殊なライトを使用して太陽光に近い光を目から取り込みます。保険適用外ですが睡眠障害外来などで受けることが可能です。
②栄養バランスの摂れた食事
幸せホルモンと呼ばれる脳内神経物質のセロトニンは感情や気分のコントロール、精神の安定に関与します。そのセロトニンの材料である必須アミノ酸の1つのトリプトファンを摂取するのが大切です!動物性たんぱく質の肉や魚、豆腐や納豆や卵やバナナに多くトリプトファンは含まれています。
心身一如
西洋医学では心と体を切り離して病気の体を治療しますが、東洋医学には心と体は一体であるという心身一如の考え方があります✨
「病は気から」という言葉があるように、心と体は密接に繋がっています。恐怖や怒り、悲しみやストレスなどがある場合は体にも力が入りやすくなるのでちょっとした刺激でも過敏に反応します。
うつ病などの精神疾患がある方は体の緊張が強いです💦
この状態が続くと自律神経のバランスが崩れるので体の痛みやだるさや疲れが取れないといった様々な体の不調を引き起こし、心も不安定になりがちです。
心も弱ってくると食欲不振もしくは食べても食べても満足感が得られなかったり、買い物依存症やアルコール依存症にも陥りやすいです。
心と体の負のスパイラルを断ち切るためには体の緊張を緩めたり、五感を使った行動をすると変化が出やすくなります😊
美味しいものを食べたり好きな音楽や香りなどに触れてください。体
の健康のためにはバランスの摂れた食事が必要ですが、体の健康は心の健康にも繋がるのでバランスの摂れた食事により心も健康になります。
体が緊張しているときはどうしても呼吸が浅く早くなりがちです。「息を詰める」や「息を殺す」など呼吸を止める動作を表す言葉も多く存在しますが、簡単に体の緊張を緩める方法としては“深呼吸”もおすすめです💫
副鼻腔炎(蓄膿症)
鼻をかんでもすっきりしない、風邪が治ったのに鼻詰まりが続く、寝るときや横になったときに鼻水が喉の方に流れる
などの症状に心当たりがあれば副鼻腔炎(蓄膿症)かもしれません💦
副鼻腔は鼻の周りにある空洞で前頭洞、篩骨洞、上顎洞、蝶形骨洞と4つが対になり計8個あります😊
鼻の中にある菌に炎症が起こると鼻の粘膜が腫れたり粘り気のある鼻水が出てきます。通常なら副鼻腔から分泌される分泌物や異物は副鼻腔の外へ排泄されるのですが、鼻の粘膜が腫れたり粘り気のある鼻水が出ることにより鼻腔が狭くなりうまく排泄されず副鼻腔内に膿として溜まってしまいます。
炎症が起きる原因として風邪、花粉症などのアレルギー性鼻炎、虫歯などがあります。虫歯は副鼻腔の1つの上顎洞が歯の根元に近いため歯の炎症が副鼻腔に移りやすいです。
🔷症状としては
①鼻水
急性期は膿の混じった鼻水だが、慢性期だと白い粘りのある鼻水
アレルギー性鼻炎ではサラサラとした透明な鼻水が特徴的です
②後鼻漏
鼻水が喉に流れて咽頭炎や気管支炎の原因にも繋がります
③鼻詰まり
鼻腔や副鼻腔の粘膜が腫れたりポリープになったりすると鼻詰まりを起こします。鼻詰まりが続くと口呼吸になったり匂いが嗅げなくなります
④痛み
急性期は頬や両眼の間の痛みや額の痛みで、慢性期は頭の重だるさや倦怠感などがあります
🔷治療として
薬局では直接鼻にスプレーをかけたり、錠剤や漢方薬があります。
病院では膿の吸引や薬剤を霧状にして鼻から吸入するネプライザー治療、抗生物質・抗炎症薬・排膿薬など内服薬の処方で重症の場合は手術になります。
副鼻腔炎などの鼻の疾患には
🔹上星(じょうせい)顔の中央ラインで髪の生え際より約2cm後ろのツボ
🔹印堂(いんどう)眉間の中央のツボ
🔹迎香(げいこう)両小鼻の横のツボ
が効果があるのでぜひ試して見てください😊