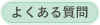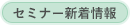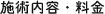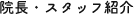Blog 3ページ目
腸腰筋
「段差がなくてもつまずきやすくなった」「片足立ちの状態で靴下を履けなくなった」という声を聞きます。心当たりのある方は体幹の筋肉が弱ってきているのかもしれません💦
腸腰筋という筋肉は上半身と下半身を繋いで体幹の安定をしてくれる大事な筋肉です。深層にある筋肉なので触りにくいですが、歩いたり踏ん張ったりするときも使います。
腸腰筋は腸骨筋と大腰筋という2つの筋肉に分かれます。
腸骨筋は骨盤と大腿骨を繋ぐ筋肉
大腰筋は腰椎と大腿骨を繋ぐ筋肉
腸腰筋を鍛えると姿勢が良くなったり下腹部の引き締めにも効果があります。腸腰筋のトレーニングには足踏みがおすすめです😊膝と股関節を直角にしっかり曲げて50回のほど足踏みをするだけです。ただし体幹が後ろに反れたり、しっかり足を上げないと効果が薄くなってしまいます😥
筋肉はサルコペニアという現象で加齢により減っていきます。それにより何も運動をしないと筋力低下による歩行困難などになり、将来的にはロコモティブシンドローム(運動器症候群)になる可能性が高くなります。
年齢を重ねてもトレーニングによって筋肉をつけたり、筋肉量をより増やすことができます。健康な身体で過ごせるように体幹の筋肉を増やしていきましょう!!
のどの詰まり(梅核気)
忙しかったり、疲れが取れなかったりすると
🔹のどの異物感
🔹のどが詰まって息苦しい
🔹食べ物が飲み込みにくい
🔹痰がからむ
など、のどの不快な症状を感じる方が多いです。
このような症状が出ることを耳鼻科では“咽喉頭異常症”と呼び、精神科では“ヒステリー球”と呼ばれます。
のどに違和感があって病院で検査をしても具体的な病気や異常が見つからないのが特徴です。また東洋医学では梅の種が詰まったような圧迫感という例えから“梅核気”と呼ばれます。
ストレスによる自律神経の乱れが原因となることが多いです💫自律神経でも特に交感神経の働きが優位になると、のどのあたりの筋肉が収縮するので咽喉頭や食道などが細く締め付けられます。
漢方薬では半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)で治療することが多いです。ヒステリー球以外にも神経性の胃腸障害や喘息、気管支炎でも用いられます。
のどの周りの筋肉が硬くなっているので筋肉を伸ばすストレッチやツボ押しなどもおすすめです😊
《ストレッチ》
鎖骨の下に手をクロスに重ねて置き、顔を真上に向けたまま口をすぼめたり、口角を広げたりします。
このストレッチは2重あごやフェイスラインのたるみにも効果があります。
《ツボ押し》
鎖骨と鎖骨の間にあるくぼみに“天突(てんとつ)”というツボがあります。人差し指で3秒間押した後、3秒間離すの1セットとして5セットほど繰り返すと効果が出やすいです。
また食事では香りの強いセロリ、パクチー、春菊、みょうがなどを取り入れるのも気を巡らせるので効果があります。
ボトックス注射💉
ボトックスとはボツリヌス菌から抽出されたたんぱく質の1種です。筋肉の痙攣や緊張を抑える働きがあり顔面痙攣、眼瞼痙攣などの治療で使われます。
また美容目的で眉間やおでこのシワ、エラや食いしばりなどでされる方もいます😊
ボトックス注射と美容鍼灸を併用して受けたいとのお問い合わせがありますが、美容鍼灸は鍼をしてお肌に刺激を与えることで治癒力が高まりお肌の細胞が活性化します。一方でボトックス注射は筋肉を萎縮させることでシワを目立ちにくくするものなのでアプローチの仕方が対照的です。
美容鍼灸の施術をお受けになるにはボトックス注射後ですと3週間から1ヵ月ほど空けていただくのがおすすめです✨
胃薬
師走になり、なにかと忙しいのでストレスや暴飲暴食などで胃の不快感を感じる方が多くなってきました。胃もたれ、胃痛、胸焼けなど様々な症状がありますが、痛みを感じたら胃薬を服用していませんか?ストレス過多な現代人が服用する胃薬にも種類があります😊
消化に関わっている胃酸はpH1〜2の強い酸性でできています。おいしそうな物を見たり、匂いを嗅いだり、食べ物が胃に入ってくると胃酸が分泌されます。食べ物の消化や食べ物と一緒に入ってきた菌の殺菌をしています。胃酸から胃の粘膜を守るために胃の内側から粘液が分泌されます。胃酸と胃粘液のバランスが崩れて胃酸の分泌が過多になり、胃の粘液の分泌が減ると胃の粘膜が傷つき胃炎・胃潰瘍になるリスクが上がります💦
《原因》
🔹アルコール
🔹喫煙
🔹ストレス
🔹暴飲暴食
《種類》
🔹H2ブロッカー
医療機関が胃炎、胃潰瘍などで処方される。第1類医薬品
🔹制酸剤
胸焼けや飲み過ぎなどで分泌過剰な胃酸を中和させることにより胃粘膜への刺激を緩和させる
🔹粘膜修復剤
空腹時の胃粘膜を守る。胃酸過多により胃粘膜が傷ついているので胃粘膜の分泌を促進させたり、胃粘膜の再生力を高める
慢性的に胃薬を服用し、胃酸から減少すると鉄やビタミンB12などの吸収率が悪くなります。欠乏症として貧血やまぶたのぴくつきなどの神経障害が出やすくなります。胃薬を常用すると胃酸を抑制するので食べ物を消化吸収できなくなり、体に栄養素を取り込めなくなってしまいます。栄養失調になると細胞分裂をする材料が足りないので新陳代謝が悪くなり不調に陥りやすいです😥
今一度、食生活を見直してみましょう😄
胃もたれや膨満感が気になる方は「ちゅうかん」というおへそとみぞおちの中間点にあるのツボもおすすめです✨指圧したり温めたりすると胃腸の働きを助けてくれます。
月経②
通常の体温計は3桁で表記されますが、婦人体温計は4桁表記なのでより精密に測れます!また婦人体温計はほとんどが口中用でできているので、通常の体温計のように脇で測るのでなく舌下(舌の裏)で計測します。毎朝起きたらそのまま口にくわえて測定します。
⚠舌上で測ったり、体を動かしてから測ると0.04~0.10℃の誤差がでることもあります。
基礎体温には低温期と高温期があり、一定のサイクルで繰り返されています。
🌸低温期…月経周期の月経期と卵胞期
🌸高温期…月経周期の排卵期と黄体期になります。
黄体期に黄体ホルモンの分泌により低温期より0.3~0.6℃くらい基礎体温が上昇し、月経前までの10~14日間続きます。
16日以降も高温期が続く場合は妊娠の可能性もあります。
またおりものの状態でもおおよその月経周期が判断できます。おりものは粘液や膣の分泌液などが混ざり、膣の潤いを保って菌の繁殖を防ぎます。
🌸月経直後…おりものの量が少なくてさらさらしている
🌸排卵直前…最も量が多く、糸を引くような粘り気がある
🌸黄体期……白く濁り、粘り気がなくなる
🌸月経直前…また量が増え、おりものが黄色っぽくなる
習慣化するまでは大変ですが、次の月経の予定日や妊娠の有無、更年期障害などが基礎体温でわかります✨
月経
女性が初経を迎えてから閉経するまで平均で35~40年間あります🙂毎月5日間を月経周期とすると生涯で約6年9ヶ月を月経と向き合うことになります。
《月経周期》
28日前後(25~38日の間であれば正常)です✨
月経周期には月経期、卵胞期、排卵期、黄体期の4種類があります。
🌸月経期
妊娠しなかったときは黄体ホルモン、卵胞ホルモンの分泌量が減り、子宮内膜が剥がれ落ちて血液と一緒に排出されます。
🌸卵胞期
卵胞刺激ホルモンの働きにより、卵巣にある卵胞の1つが発育し始めます。卵胞ホルモンが分泌され子宮内膜が厚くなります。
🌸排卵期
排卵日を挟んだ2~3間。人によってはこの時期に"排卵痛"という下腹部の痛みや少量の出血があります。
🌸黄体期
排卵後の黄体が変化します。妊娠時の準備の為、子宮内膜がより厚く柔らかくなります。
《月経の日数》
3~7日が正常 日数が短すぎるのも長すぎるのも問題があります
《月経の量》
約20~140gと言われていますが、ピンとこないかと思います。1~3日目でナプキンやタンポンが1時間もたないと多いです。月経の2日目までで1回の月経の8割が排出されます。逆に2、3日目でも1日中ナプキンを替えなくてももつ場合は少ないです。
月経は正常だと毎月くるので月経と上手に向き合っていく為にも基礎体温を測り、月経周期を把握することがおすすめです😊当院のお客様でも妊活をされる方がおりますが、3ヶ月分の基礎体温のデータがないと産婦人科で治療ができません💦
下肢静脈瘤
夏に比べて水分の摂取量が減り気温も低くなってきたので、血流不足により足がむくんだり重だるさを感じる方が増えています。女性は特にふくらはぎの筋肉が少ないのでむくみやすくなりますが、むくみが悪化すると下肢静脈瘤にも繋がります。
足先に行き渡った血液が心臓に戻るとき重力に逆らって上がっていきます。歩いたりしてふくらはぎの筋肉を使うことにより血管を収縮させています。途中で逆流をしないように静脈弁が支えていますが、筋肉のポンプ作用が低下したり静脈弁が壊れたりして静脈が太く膨らんだのが静脈瘤です。
《原因》
遺伝や妊娠出産経験のある人や立ち仕事の人に多いとされています。妊娠出産などはホルモンの影響で静脈弁が壊れやすくなります。第1子よりも第2・3子出産後の方がなりやすいです。美容師や調理師、教師など1か所に立ってあまり動かない人もなりやすいです。
《症状》
血管が浮き出る、足のむくみ、足のだるさ、疲れやすい、足のほてり、足がつるなどがあります。
《種類》
くもの巣状、網目状、側枝状とされるものは軽症で太もも外側や膝内側、くるぶしにできやすいです。重症化しにくいので見た目が気になる人以外は治療しません。
伏在状はぼこぼこと4mm以上の血管が浮き出てうっ血性皮膚炎や潰瘍などが起こり重症化したら手術が必要となります。
むくみの多くは生活習慣や加齢などで起こりますが下肢静脈瘤以外にも甲状腺機能低下症や妊娠中毒症や心不全などの病気でもむくみの症状が起こります。急にむくみの症状が悪化した場合は医療機関の受診をおすすめします。
下肢静脈瘤の予防や進行を遅らせるために
①湯船に浸かる
②かかと上げ運動
③医療用弾性ストッキングや着圧ソックスの着用
などをして下肢の血流を良くするのが効果的です。
甘酒
甘酒は日本伝統の発酵飲料ですが、最近の研究で美容や健康の効果が高く見直されるようになりました。その効果の高さから“飲む点滴“や“飲む美容液“とも呼ばれています。
甘酒には米麹で作った甘酒と酒粕で作った甘酒の2種類があります。
《米麹》
蒸したお米に米麹と水を混ぜて55〜60度の温度で数時間発酵させます。砂糖を入れなくてもお米のデンプンの甘みがあり飲みやすいです。
《酒粕》
日本酒を作るときにです酒粕を水に溶かして砂糖を加えて煮込みます。酒粕に含まれるアルコールが微量ですが残ります。
甘酒には疲労回復や便秘予防、熱中症予防などの効果があります。
①疲労回復
ブドウ糖は腸管からの吸収率が高いので素早く吸収されてエネルギー補給になります。甘酒の約20%がブドウ糖で出来ています。甘酒は江戸時代のエナジードリンクとされるほどの人気のある飲み物でした。
②便秘予防
甘酒にはレジスタントプロテインという食物繊維や腸内細菌のえさになるオリゴ糖が含まれているので腸内環境の改善の働きがあります。また慢性的な便秘の方は顔の吹き出物が出来やすくなります。
甘酒にはビタミンB群が豊富に含まれており、ビタミンBはエネルギー代謝や皮膚の代謝を良くしてくれるので美肌にも良いです。
④熱中症予防
暑い時は汗をかくことにより体の熱を下げますが、汗と一緒に体内にあるナトリウムも排泄されます。体内のナトリウムが少なくなると濃度を一定にする為に喉の渇きが感じにくくなります。水分補給には塩分と糖が含まれている飲み物が効果的です。厚生省が熱中症の予防をするには100mlあたり40〜80mlのナトリウムが含まれている飲み物で水分補給をするのが適しています。甘酒にはおよそ60mlが含まれています。
プロテイン
近年は健康意識が高まりジムやヨガ、ピラティスなどに通う方が増えてきました。トレーニングに伴いプロテインを飲んでる方もいるかと思います。
プロテインとは英語でたんぱく質です。牛肉・豚肉・鶏肉などの肉類、魚類、卵、チーズや牛乳などの乳製品、大豆などにたんぱく質は含まれています。
体の中では骨や肌などを作るコラーゲン、髪の毛や爪のもとになるケラチン、血中に存在するアルブミンがたんぱく質です。
プロテインで主流なのは乳製品(動物由来)のホエイと大豆(植物由来)のソイの2つです。ほかにもカゼイン、エッグ、ピープ(エンドウ豆)などもあります。
ホエイはヨーグルトの容器を開けたときの上澄みの乳清と呼ばれる液体のとこです。ホエイプロテインは比較的吸収が速く、筋肉をつけるのに有効的なアミノ酸が入っています。ホエイプロテインには乳糖が含まれているものもあります。牛乳を飲むとおなかが緩くなるという乳糖不耐症の方は適していません。
ソイは大豆が原料で、アルギニンというアミノ酸が豊富に含まれています。ゆっくり吸収してくれるので体のウエイトを増やさずにボディメイクをしたい方はソイプロテインが向いています。また大豆には女性ホルモンに似た働きをしてくれるイソフラボンが入っているので女性におすすめです。
プロテインを飲むタイミングは運動前、運動後、就寝前が適しています。運動前だと摂取したアミノ酸を使って燃焼できるのでダイエットにも効果的です。運動後だと筋トレでたんぱく質の吸収が良くなるので運動後30分~45分以内に飲むのがおすすめです。就寝中は栄養を摂ることが出来ないので就寝前30分~1時間前に飲むのも体にとって良いです。
プロテインを飲む目的に応じて種類や飲むタイミングを選んでくださいね☺
冬の養生
どんどん気温が下がり冷えや体の凝りが気になる方が増えてきました。またこれからのシーズンは忘年会や新年会などがあるので胃腸の調子を崩す方も出てきます。少しでも体が楽に過ごせるように冬の養生法としては「睡眠」と「冷え対策」が大切になってきます☺
①睡眠
冬は日照時間が短く、寒いのでどうしても睡眠の質が悪くなりやすいです。いつもと同じ睡眠時間でも朝すっきり起きれなくなります。冬は「早寝、早起き」ではなく、「早寝、遅起き」をするぐらい睡眠時間をしっかり確保するのがおすすめです。
また体が冷えた状態では寝付きが悪かったり、眠りが浅かったりします。寝る1時間半~2時間前にお風呂に入るのも睡眠の質を良くしてくれます。約41℃の湯船に5~10分程浸かるだけで深部体温が機会的に上がるので、1時間半~2時間後に深部体温が下がり寝付きがスムーズになります。
起きてからは朝日を浴びて下さい。浴びることにより体内時計がリセットされ、睡眠を促すメラトニンというホルモンが約16時間後に分泌されます。太陽の光を浴びないと、気分が落ち込みやすい・集中力が低下してやる気が出ないなどの冬季うつになるリスクも高くなります。
②冷え
「冷えは万病のもと」といわれるように冷えると足のむくみ、体の凝り、生理痛が重くなるなどの体の様々な症状を引き起こします。おなかや腰に手を当てて手の方が温かく感じたら内臓冷えになってるのでカイロをおなかや腰の辺りに貼ったり、重ね着をして温めて下さい。
忘年会や新年会などで体の内側から冷えて胃腸に負担がかかりやすくなります。冬が旬の根菜類を意識して食べて体の内側からも温めましょう!